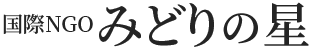大気浄化

樹木全体に粘着性があり、葉・幹・枝・種子殻まで花以外全てに強い粘着性があります。特に1、2年生の葉は大きい物では1mを超え、柔らかい葉にはびっしりとした繊毛。そしてその粘着性で、小さい飛翔する昆虫~大気汚染物質~匂いの分子まで大気を濾し取り、浄化します。揮発性有機化合物(VOC)の削減、黄砂、PM2.5は無論の事、飛散花粉の除去にも効果を発揮します。(花が咲き終わる5月に入れ替わるように葉が大きく成長します。それまでは効果が一部抑えられます。)
緑化・日陰・騒音吸収

緑化
桐は景観植物で、観る者にやすらぎを与え、大きな葉が作る日陰は住民を守り、美しい花と高貴なその香りはそこに集う人の喜びです。生活に緑を取り入れることは重要です。さまざまな汚染除去能力がありながら、唯一と言っていいアレルゲン物質が全く存在しない健康で安全な樹木です。
日陰
桐は比類なき成長力を持ち、植えた最初の年に、3~4m成長し、2年目には6~7mに、そして3年目には9mに成ります。
急速に成長するので短期間に整備が必要な場所、その大きな葉で夏期の日陰が確実に欲しい場所等の、例えばイベント会場などに打って付けです。
騒音
世界の公園都市で使用され、大きく柔らかい葉が街の喧噪を吸収します。また目隠し効果が高く、騒音を抑えるため、工場緑化として、森の中の工場ではなく工場内に森を作ることも可能になります。
環境臭の除去

大きな葉が大量のCo2を吸収し、匂いの分子を除去、周囲の空間をオゾン化します。それにより、環境臭の除去に貢献しています。ベルギー委員会は、塩化水素を大気中に放出する産業・企業に対し、成長の早い木を植える事を義務付けています。米国でも硫化水素などの有害な不純物を大気から取り除くために使用されています。
ファイトレメディエーション

ファイトレメディエーションは、植物の自然なプロセスを活用して汚染物質を除去する手法です。桐はその一環として活用されています。アメリカでは硫化水素汚染の工業用地や造園地域で栽培され、スウェーデンでは汚水処理に利用され、廃棄物を肥料として再利用します。育った桐はバイオマス燃料にもなります。チェルノブイリでは、桐が放射性元素を吸収する能力を活かして植林され、土壌、水、空気の浄化に貢献しています。
最近注目されているP.F.A.S.は、温室効果が非常に強力で分解されませんが、桐はこれを幹に閉じ込め、環境汚染を除去する役割を果たします。
Biomass・Bio Fuel

Biomass
桐の着火温度は425℃です。
杉・松などの260℃と比較して非常に高温できれい(灰の量が1/40)に燃焼するためボイラーを痛めません。また、1,000tのBiomassを作る過程で年間100tのCo2を吸収します。燃焼時のCo2発生量は187kgです。はるかに多くのCo2を吸収し、極僅かのCo2しか排出しない桐には「ネットゼロ」という呼称は当てはまりません。
桐のBiomass農園では、植林後2~3年後に最初の収穫、その後2年に一度の収穫が繰り返されます。月齢17ヵ月のCo2固定量はヘクタール当り11.04トン(CIEMAT)、Biomassは収穫後自動再生されるので再植林も不要となります。
Bio Fuel
Biomassにも言える事ですが、円安などの為替変動や国際価格高騰などに影響されず、安定供給が図れるのが桐による改革です。桐はツリー油田と言われており、数年前の米国研究機関では桐1tから511Lのバイオ燃料を作りました。コロナ前の2020年の時点で既に、フランス全土の70%のガソリンスタンドではバイオ混合燃料が販売されていました。
その後のロシアによるウクライナ侵攻後の燃料不足が発生した際、フランスでは畑から作られたバイオ燃料により燃料不足が一切起こりませんでした。またバイオ燃料は高性能であり、車のリッターあたりの走行距離が伸びることが確認されています。
Timber
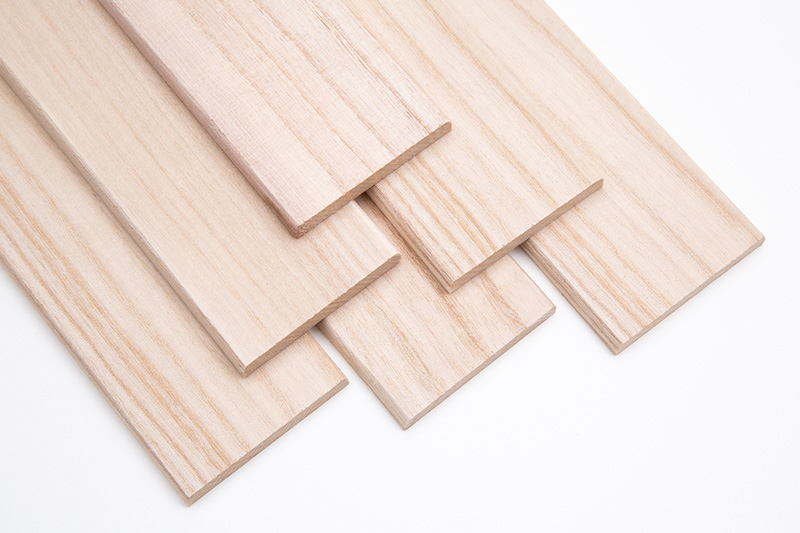
桐は優れた材質性能を持ち、熱を伝えにくく、温度差による結露を防ぎます。また、柔らかく弾力性があり、転倒時に怪我をしにくいバリアフリー効果があります。さらに抗菌性に優れ、カビや白アリを防ぎ、火に強く火災リスクを減らします。切断面が綺麗で変形せず、経年変化に強いといった特徴がある素材です。
家具や彫刻、楽器、音響機器などに使用され、軽さと耐摩耗性を活かしてボートや航空宇宙産業、車の内装にも利用されています。正倉院の能面にも使用され、日本国や内閣府の紋章や500円硬貨のデザインにも採用されています。色白で塗料との親和性も良く、見た目は最高級のオーク材に匹敵する美しさを持ちながら、驚くほど軽い桐は、新しい製品や商品開発に大きな可能性を秘めています。
医薬品

桐属の化学成分の研究は1930年代初頭に始まりました。
日本の研究者(Kazi M,Simabayasi T)がこの分野に最初に取り組み、1931年に世界で初めて桐の樹皮と葉からグリコシドを分離しました。現在では、桐の化学組成、薬理学的効果、および潜在的な臨床応用について、世界中で研究されています。日本で一般的な桐(Paulownia Tomentosa)だけでも、23種類のフラバノンが分離されています。葉、花、実、木材、樹皮、種子、根など部位により抽出されるさまざまな薬理学的活性物質があり、薬として実用化された製品も数多く、世界中で開発研究されています。
飼料・肥料

飼料
飼料用トウモロコシの主要な生産国であったウクライナが侵攻を受け、日本のみならず世界中で家畜の餌不足が発生しています。特に輸入量が多い日本はひっ迫し、止む無く廃業の憂き目にあった生産者もいます。桐の葉は栄養価が高く、特にエネルギー、タンパク質(葉の18~20%)、カリウム、マンガン、カルシウム、リン、亜鉛が豊富に含まれています。鶏卵に最適なアロファロファより栄養価が高いと言われるほどです。またCo2の発生を抑える重要なこととして、桐の葉のサイレージ(発酵餌)には、牛などの反芻動物が発生させるメタンガス(げっぷ)を減少させる効果が証明されています。
肥料
地球の人口増が食料危機を招き、加えて世界の農地が科学肥料による土壌菌の減少により疲弊しました。そして、ウクライナ侵攻により肥料鉱物が食料安全保障の中心議題となりました。新たにEVの普及が肥料鉱物取得競争に名乗りを上げ、追い打ちをかけ始めました。肥料無しには農作物は作れません。近い将来、肥料問題は人口増の食料増産と共に地球規模の大問題となります。
桐は落葉樹です。成木一本当り約40㎏の窒素成分を含む良質肥料となり、疲弊した農地を再生することができます。つまり桐の樹間で農作物を育てる森林農法を実践することで、桐の葉の高い栄養価が土壌を豊かにしていきます。
(桐の葉の含有量の分析:アッシュ@ 550℃:7.8%, タンパク質(N×6.25):22.6%, 有機物:91.4%, リン:0.6%, カルシウム:2.1%, 鉄:0.6%, 亜鉛:0.9%, 無芽胞エネルギー:15-18MJ/KG)